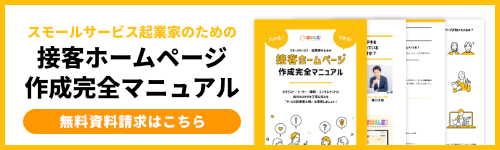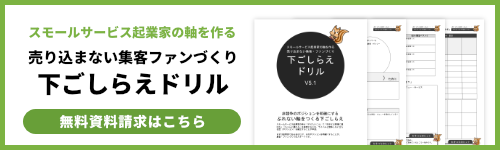- ホーム
- 保険代理店マーケティング研究会ブログ
- 「保険業法改正に伴うプロ代理店の態勢整備と実務」講師インタビュー
「保険業法改正に伴うプロ代理店の態勢整備と実務」講師インタビュー
2014/10/09
10月6日発行の新日本保険新聞(損保版)にて、保険代理店マーケティング研究会にてサポーターを務める 弁護士の吉田先生と社会保険労務士の藤井先生のインタビューが見開き1ページを使って掲載されています。
このインタビューは、今年の6月・7月に東名阪で行われた、新日本保険新聞社主催のセミナー(協力:損保ジャパン日本興亜社)「保険業法改正に伴うプロ代理店の態勢整備と実務」の総括として行われたもので、当日セミナーに参加できなかった代理店店主の方にもわかりやすくセミナーの論点がわかるものとなっています。
業法改正での最重要ポイントは「募集人への移行把握義務・情報提供義務の導入」「代理店への態勢整備義務の導入」
インタビュー冒頭で、吉田先生が今回の保険業法改正の最重要ポイントを聞かれて
大きく分けると2つあります。
1つは新しい募集ルールとして、募集人を規制対象に『移行把握義務』と『情報提供義務』が導入されること。
もう一つは、保険代理店も一つの企業体として『態勢整備義務』が課せられることです。
(吉田氏)
と答えています。
そして、この2つの最重要ポイントに保険代理店が対応していくために取り組むために必要なのは
お客様との一つひとつのやり取りをエビデンス(証拠・記録)として残しておくこと
(吉田氏)
改正保険業法の最重要ポイントは
「募集人への移行把握義務・情報提供義務の導入」
「代理店への態勢整備義務の導入」
対応のキーワードは「エビデンス」ですよ!
体制整備ではなく、態勢整備を
吉田先生がセミナーでも強調していたのが
「体制整備」ではなく「態勢整備」が必要
ということ。
当局はまさに”体制”ではなく”態勢”を求めています。
”体制”は会社としての枠組み・形を作ることを言い、内部規定の策定や組織を作ることを言います。そして、それが実際にきちんと機能していることを”態勢”と言います。
例えば百頁にもおよぶ内部規定を作っても、難しくて募集人が読まない・理解しないのなら、”態勢”ができているとはいません。
(吉田氏)
ここは、強調しても強調し足りない部分ですね。
代理店店主さんとお話していても、なんとか「体制」だけの整備で逃げられないか、ということをおっしゃる方がおられますが
そういう姿勢では危ないということを肝に命ずるべきでしょう。
体制の整備は付け焼き刃でも可能ですが、態勢となると
体制を整備して、態勢になるまで実施・検証が必要になりますから、かなりの時間を要することがわかります。
再来年4月の施行ですが、態勢整備は保険代理店が今すぐ取り組むべき課題ですね。
委託型募集人適正化問題は保険業法と労働法の両面で対応が必要
話題は変わって、藤井先生へのインタビュー。
焦点はいわゆる、委託型募集人の適正化について。
ここでもやはり「態勢」が大切であるとの声が。
やはり、労働法の観点でも”態勢”のほうが大事です。それこそ形だけパート契約を結ぶというのは”体制”で、そうでなく実態で判断しますので。
(藤井氏)
書類や呼び名だけでなく、勤務実態が大切ということですね。
つまり、形式だけ整えて・・・というのは通用しないということでしょう。
態勢整備をチャンスに変える
最後にまとめとして吉田先生の言葉をご紹介します。
コンプライアンスの態勢整備をしたら、それをホームページでアピールしてもらいたいですね。
保険に加入するのは、いわゆる自分のセンシティブな情報を渡すということなので、その面の安心感はこれからお客様に選ばれる重要な基準になってきます。
(中略)
態勢整備として取り組んだことも、まさに営業ツールとして活かすことができることになります。
(吉田氏)
法律が変わることは避けられません。
保険代理店として取り組まなければならないことがたくさんあり対応はとても大変ですが、
逆にキチンと態勢を整備することで、
お客様に対する武器にする。このような姿勢でマーケティング活動の一環としてもアピールできるのではないでしょうか。